My darling, believe me
For me there is no one but you
Please love me too
And I’m in love with you
Answer my prayer now, babe
「I say a little prayer」(小さな願い)
この曲を私がはじめて聞いたのは、
ディオンヌ・ワーウィックのヴァージョンでした。
バカラックは、いわゆるゴスペル風のヴォーカルを
自分の曲にのせるのがあまり好きではなかったので
ワーウィックのようなヴォーカリストをわざわざ選んでいた
という話を聞いたことがあって
その真偽のほどは定かではないところもあるのですが
でも何となく納得できる話として記憶しています。
ハル・デイヴィッドの歌詞は
ブロークン・ラヴソングばかりで
この歌詞を情感たっぷりに歌い上げられたら
ちょっと「トゥー・マッチ」な感じはするな~と
(カーペンターズのバカラックで育った私は)思っていたからです。
そんなこともあり、アリーサ・フランクリンのヴァージョンを聞いたときは
ぶったまげました。。。
これでもか~というぐらいの情感(情念というべきか)で
歌い上げる彼女のヴォーカルは当時の私には
一種、カルチャー・ショックのような体験として感受されたのです。
これは可愛らしい「小さな願い」ではなかったと。。。
バカラックがいわゆる白人中間層向けの音楽として作った
当時としてはお洒落っぽい曲の深層をえぐりだしているかのような
感じさえしました。
プロデューサーは後にクリームやエリック・クラプトンの作品などを
手がけた名匠トム・ダウド。
この人、ウィキペディアによると
「コロンビア大学の物理学研究室に勤務し、第二次世界大戦中だった18歳の時に徴兵されて工兵として原子核工学を研究。それはマンハッタン計画に関わるものだった」とあり、さらに
「音楽と物理学の知識を生かしたトムの音作りは、1949年には既に評判となり」云々。
原爆製造からソウル・ミュージックのエンジニアへの転身とは
恐るべき(語弊はあるけれど)「アメリカン・スピリッツ」。。。
閑話休題。
アリーサの「I say a little prayer」は
ソウル・ミュージック側からの「レスポンス」ではあったのでしょう。
そしてトム・ダウドがクリームを介して、その「コール」に応えたというか
ロック・ミュージック側が応えた感じが私にはするのです。
ちょっとうがった見方かもしれませんが
バカラック流のポップスを終わらせる時代精神の先駆けを
この一連の流れに見るような気がして
ちょっと書きたくなってしまいました。。。
だからアリーサ自身、スピリッツとしてロックを理解できた人だったのだ
と思います。
つまりあの感情の爆発のような彼女のヴォーカル・スタイルは
単にゴスペル畑の出自だけにはよらないものだったのではないでしょうか。
まあハード・ロックを歌うアリーサを夢想しているわけではありませんが。。。
ゴスペル・シンガーのエリートとして育てられ
公民権運動やフェミニストの時代と
彼女のポップスターとしてのブレイクがクロスしたために、
その象徴的な存在でもあったアリーサですが
私生活ではけっして恵まれていたとは言えず
70年代後半以降のキャリアの低迷などもありました。
でも、めげずにチャレンジしていく彼女の姿は
いろいろな意味で「アメリカ」っぽかった。。。
Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman – Kennedy Center Honors 2015
https://www.youtube.com/watch?v=XHsnZT7Z2yQ
この晩年の映像を見ると、
近年までとてもパワフルであった歌声に驚かされます。
ご冥福をお祈りいたします。

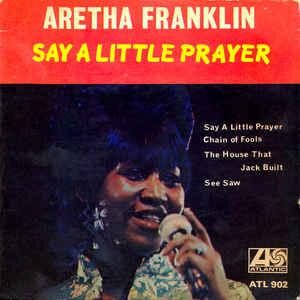
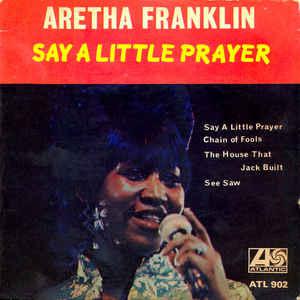
コメント ※編集/削除は管理者のみ