我が家の裏庭的なスペースには
つる性の羽衣ジャスミンが植わっていまして
ここ10日ほど、あのちょっと官能的な感じのする香りを
漂わせて咲いております。
とりわけ朝晩は薫り高く
私はなぜか忘れていた何かを思い出させられるような気分に
なってしまうのですが
そんなGW初日の今日
みなさんはいかがお過ごしでしたでしょうか。
母の1か月余りの入院で
久々のひとり暮らしとなった私でしたが
年老いて体力も衰え、
いろいろな面での判断力も失いつつ
(コロナ禍で面会もできない)孤独な入院生活を送る家族のひとりを
思いつつの暮らしは、当然と言えば当然ですが
重い塊を飲み込んでいるかのようなものとなりました。
しかし現実の生活の中では、また別な意味での寂寥感として
表れてきたのでした。
それは「生活のサイズ感の変化」とでもいうべきものでした。
わかりやすいところで言えば
部屋がガランとしてしまった感じ。
どこかうすら寒い感じ。
また買い物の量も減らさなければ、
食料品も余ってしまうようになりましたし
ゴミも減る、トイレットペーパーの使用量も減る。。。
そんな具体的なことで孤独な思いが表れてくるとは
想像していませんでした。
そして退院後10日あまり、自宅で母の最期を看取ることとなりました。
というわけで聞く音楽も知らぬうちに限られてきてしまうところもあって
なぜか私の場合、ハイドンなのでした。。。
とりわけよく聞いていたのは
ジャン・ロンドーの新作『パルナッソス山への階梯』でした。
https://www.hmv.co.jp/en/news/article/230113102/
このアルバムのコンセプト等について興味ある方は
リンクを見てくださるとありがたいですが
ピアノ曲として演奏されることの多い楽曲を
ロンドーがチェンバロで演奏していると考えておけばよいかと思います。
とにかくこの中で演奏されている
ハイドンのピアノ・ソナタ第31番変イ長調 XVI:46が
とても気に入ってしまったのですね。。。
おそらくこの曲はチェンバロで作曲された
(あるいはチェンバロで演奏されることを想定していた)
のじゃないかと思うのですが
意外にチェンバロで演奏されているCDは少ないようです。
また(たぶん大宮真琴さんの『ハイドン新版』の中で
紹介されていたと記憶していますが)
「ハイドンはひとりでいるとき
チェンバロを自由に弾くのを愉しみにしていた」そうなので
彼自身のそんな姿も浮かんでくるという感慨が
私にはありました。
悪妻との冷え切った家庭生活の中で
ひとりチェンバロに向かっていたハイドン。。。
孤独ではあったろうと思いますが
だがそれゆえに彼の弾くチェンバロは
いっそう甘美な調べであったのじゃないかな~。
そんなことを感じさせるロンドーの演奏でした。
ただ、このソナタの演奏は表現としても、
ピアノより、短調化する時のメランコリックで激しい内面的な感じなんかは
ずっと優れているのでは。。。などと言い放ちたくなるほどで
メラメラした白い炎を纏っているように
私には聞こえました。
さらにロンドーの独奏作品としても
私はこのアルバムをいちばん気に入っています。
彼の自意識を最も感じない演奏と言いますか
素直に音が入ってきやすいのです。
その分、いつもの独奏作品より、逆に彼の情熱が伝わってくる。
でも選曲は、思いっきり彼の自意識が表れているんですけどね。。。
何しろこのアルバムにちなんだ自作の短編小説まで
付けているぐらいですから。
ちなみにその中で「あのハイドンのソナタはどう弾いたの?」と問われ
主人公のジョ―は「狂気と喜びで、だと思います」と答えています。
次によく聞いていたのは
『ハイドン:6つのディベルティメント』(ジトヌヒナ/ラマザノヴァ/
シュトライヒ/ブロック/ゴルノフスキー)です。
https://ml.naxos.jp/album/GEN22560
「Joseph Haydn Divertimento in D-Dur Hob.4-6 for Flute, Violin and Cello」
https://www.youtube.com/watch?v=mzHo9SR9Itc
これはほとんどストレスを感じないアルバムなんです。。。
ちょっと珍しいのは、前半がピリオド楽器による演奏で
ジトヌヒナはトラヴェルソを吹いていますが
後半はモダン楽器なのでフルートに持ちかえているところです。
ゆったりとしたテンポやリヴァーヴの感じもちょうどよろしく
ポカーンと聞くもよし、作業用BGMとしてもよしってところです。
こういう感じは(微妙なところでありますが)
モーツァルトやベートヴェンではどうかな?と思ってしまう自分がいて
同趣の曲でも、二人の場合、激しさの痕跡を感じてしまうような気がして。。。
やはり自意識を感じさせないハイドンがいいんですね。
3枚目は、ジョヴァンニ・アントニーニ指揮 、
イル・ジャルディーノ・アルモニコ 演奏による
『ハイドン2032プロジェクト13 – ホルン信号』
(交響曲第31番、第48番、第59番)です。
https://lnk.to/Haydn2032Vol13ID
「Alpha」レーベルですすめられている
ハイドン生誕300周年となる2032年までに
100曲以上ある交響曲を全て録音するというプロジェクトの13集目は
ハイドンがエステルハージ家の副楽長から楽長に昇進し
脂の乗ってきた1760年代後半に作られたシンフォニーで
(31番の別名にも使われている)ホルンの演奏が印象的な
3曲が選ばれています。
この当時エステルハージ家のオーケストラには
正式なメンバーとしてのトランペット奏者はおらず、
特に31番作曲当時は正式なホルン奏者が4人もいたとのことで、
現代の感覚で言うとトランペットが担ってもおかしくないようなパートを
彼らが演奏しています。
(このあたりの事情に関しては
ナチュラルトランペット(無弁)は演奏が難しく
ハイドンやモーツァルトの時代には名人とよばれるような奏者が
少なかったという説明を読んだことがあります。)
アルバム冒頭(31番の第1楽章)なんかは重厚なホルンによる
華々しいファンファーレが続いていくようで
朝いちばんに聞くと、体の芯から目が覚めます!
このあたりはトランペットのそれとはずいぶん質感が違います。
どことなくオリエンタルでアルカイックな感じ
といったらいいんでしょうか
低い読経の声のユニゾンとともに聞こえてくる
チベットの長いラッパを聞いているかのような印象が
私の中でダブってくるのです。。。
このプロジェクトのすべてのアルバムに解説文を寄せている
音楽学者のクリスティアン・モーリッツ=バウアーは
このアルバムの解説の最後に次のようなメッセージを残しています。
「先入観を持たずに、ジョバンニ・アントニーニと
イル・ジャルディーノ・アルモニコの音楽家たちが奏でる音に
身を任せてください。
ハイドンの音楽が、憂鬱な気分になりがちな王子に効果を発揮したように。」
ちょっと謎めいた感じではありますが
このアルバムを聞き通すと、なんだか納得できてしまうのですね。
アンニュイな気分を吹っ飛ばすエネルギーを
もらっている自分がいるからです。
いわゆる「元気をもらう」ってやつです。。。
加えて、ホルンが他の木管楽器や弦楽器と溶け込んで聞こえる
そんな魅力のようなものについても再認識しました。
「俊敏系」の演奏を身上とするであろう
イル・ジャルディーノ・アルモニコのハイスピードな合奏においても
ホルンは見事に溶け込んでいるように感じました。
さて、どのようにこの日記を終えようか。。。
ふわふわとした
あてどなく彷徨う魂の落ち着き先は
どこにあるのかわかりませんが
これから何年、ジャスミンの咲く季節を迎えても
思い出すべき対象を見つけたという意味では
ハイドンの音楽とともに
今年の記憶は格別になりそうな気がする。。。
そんなことは書き留めておいてもいいかな~
と思った私なのでした。

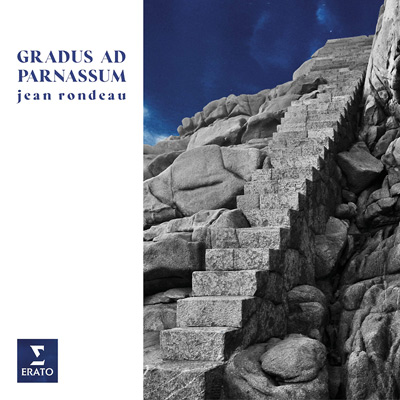
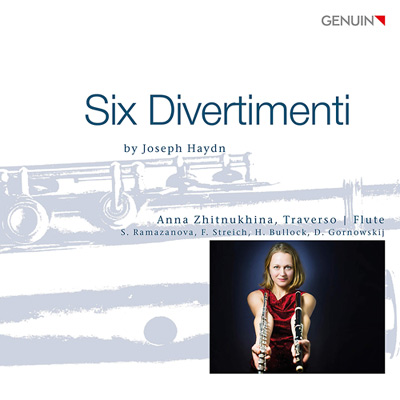
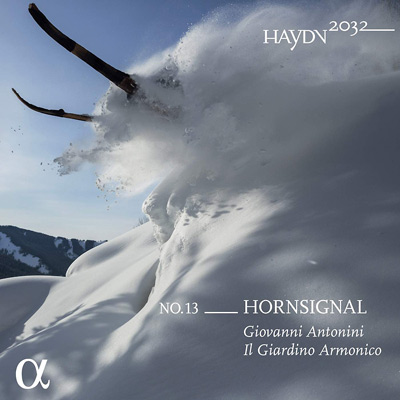
コメント ※編集/削除は管理者のみ
ゲオルグさん、こんばんは。
「ホルン信号」に反応してしまいました。
古楽器による演奏はストラヴィンスキーあたりの時代に下ったものに至るまで色々と試みが成されていますが、やはりハイドンあたりが一番ハマる気がします。
イル・ジャルディーノ・アルモニコは好きな古楽団体なのでこの録音プロジェクトには注目していますが、弦の切れ味良さと管のナチュラルな響きが混ぜ合わされた、弾けるような演奏がハイドンににぴったりで良いですね。
…と思いつつも、何故か「ホルン信号」に関してだけは100年近く前((1929年録音!)のこれがお気に入りです(笑)
http://www.yung.jp/yungdb/op.php?id=4637&category_id=2
クレメンス・クラウス指揮
ウィーン交響楽団
往年の名指揮者の若き日の録音です。
自分でも何故この演奏が好きなのかよくわからないのですが、たぶんオケの勢い、ウィーンの奏者のフリーダムさをうまく曲の枠組みでしっかりまとめている指揮、のバランスがツボにはまっているのかもしれません。
眠り猫さん
おはようございます
レスありがとうございます!
ご紹介のクラウス指揮ウィーン交響楽団の演奏聞いてきました。いや~いい音してますね~。とても1929年の録音とは思えないです。。。おっしゃるように弾けるようなイル・ジャルディーノ・アルモニコの演奏と比べると、なんともたおやかですね。第2楽章はアンダンテなんで、これくらいゆったりしていると演奏がばらついてしまうようにも思えるのですが、弛みを感じさせないのは、クラウスがバランスをうまくとっているからなんでしょうね。
それにしても、こうした最初期の録音から最新の録音まで聞く中で、演奏のスタイルは変遷があるものの、あらためてハイドンの音楽の精神のようなものが受け継がれていっていることに嬉しさも感じました。
素敵な演奏のご紹介、ありがとうございました!